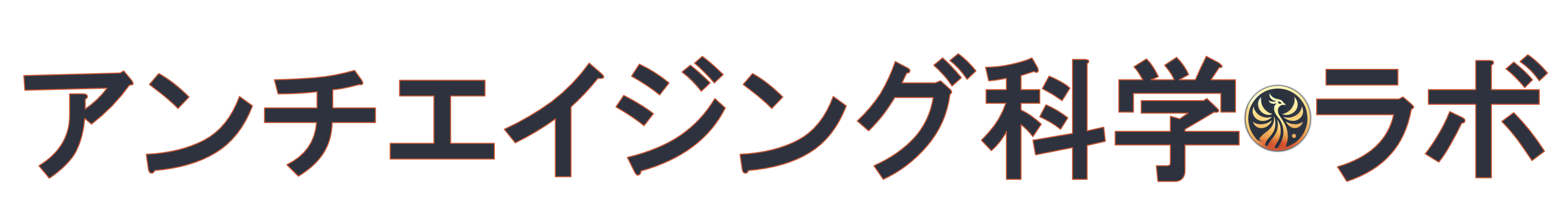【脳科学の新発見】MRI画像でアルツハイマーを91%の精度で判別!
アルツハイマー病は、高齢者に最も多い認知症の原因で、記憶障害をはじめとする認知機能の低下が少しずつ進んでいく病気です。
世界では患者数が年々増加しており、2050年には現在の4倍に達すると予測されています。
そのため「どうやって早期に発見し、進行を予測するか」が医学・脳科学の大きな課題となっています。
🖼 MRIでわかる脳の変化
MRI(磁気共鳴画像)は、脳の構造を細かく見ることができる画像検査です。
アルツハイマー病では、海馬など記憶に関わる部分から脳の萎縮が始まり、徐々に他の領域へ広がっていきます。
これまでは「海馬の体積が小さいと危ない」といった単一の部位に注目する研究が多かったのですが、最近は「脳全体のパターン」として変化をとらえるアプローチが注目されています。
🔍 最新研究のポイント
今回紹介する研究では、約700人の高齢者(アルツハイマー病、軽度認知障害、健常者)を対象にMRIを解析しました。
特徴は以下の通りです:
・259種類の脳の形態指標(皮質の厚さ、体積、曲率など)を計測
・OPLS(直交部分最小二乗法)という多変量解析の手法を用いて解析
・「どの指標を補正すべきか?」という技術的な問題も検討
その結果、以下が明らかになりました。
皮質の厚さ(cortical thickness)は補正しない方が良い
→ そのまま使うのが一番精度が高かった。
体積(volumes)は頭の大きさ(ICV)で補正した方が良い
→ 個人差(頭の大きさ、性差など)を取り除くことで精度が上がった。
両者を組み合わせるのが最強
→ 皮質厚(非補正)+体積(ICV補正)で、ADと健常者を91.5%の精度で判別!
さらに、軽度認知障害の人が1年半後にアルツハイマー病へ進行するかどうかも予測でき、その精度は約76%でした。
💡 研究が示すこと
この研究からわかることは、
👉 MRI画像を用いた脳の形態解析は、アルツハイマー病の早期発見や進行予測に有用である
ということです。
特に、皮質厚と体積を組み合わせることで「病気になる前の変化」をかなり正確に見抜ける可能性が示されました。
🌟 未来への期待
将来的には、脳ドックなど日常的な検査でMRIを撮影し、AIや自動解析で「認知症リスク」を予測する時代が来るかもしれません。
さらに、脳脊髄液マーカーやPET検査などと組み合わせれば、予測精度はさらに高まると考えられています。
つまり、この研究は「MRIで未来の脳の健康を見通す」第一歩と言えるのです。
✅ まとめ
・アルツハイマー病は早期発見が重要
・MRIから抽出できる「皮質厚」と「脳の体積」がカギ
・適切な補正方法を用いると、9割以上の精度で識別可能
・将来は「MRI+AI」で認知症予防につながる可能性
Westman, E., Aguilar, C., Muehlboeck, J.-S., & Simmons, A. (2013). Regional magnetic resonance imaging measures for multivariate analysis in Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment. Brain Topography, 26(1), 9–23. https://doi.org/10.1007/s10548-012-0246-x